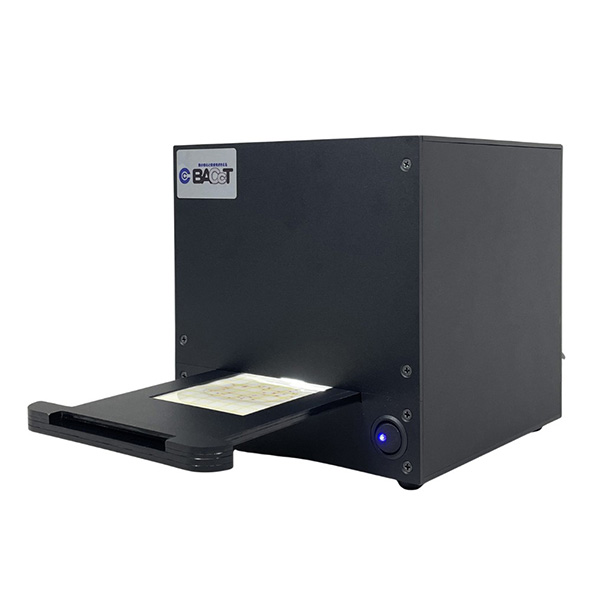今回の動画はBACcTチャンネル日本細菌検査の野﨑が株式会社陣中の代表取締役社長の福山さんにインタビュー形式で、牛タン加工会社の歩みと想いに迫ります。
料理人としての経験と、お客様の笑顔が原動力になった——そんな一人の想いから、陣中の物語は始まりました。
「美味しい」を届けることに情熱を注ぎ、牛タンを軸にした商品開発が全国へと広がっていきます。
その背景には、料理人以前の原体験と、現場で培った“気づき”があったのです。
動画は主に6つの内容で構成されています。
①起業のきっかけ
②企業名の由来
③苦しい時期は何度もあった
④「復興・観光・環境」にかける想い
⑤食品衛生に対する考え方
⑥FSSC22000を取得するメリット
では順番に見ていきましょう。
①起業のきっかけ
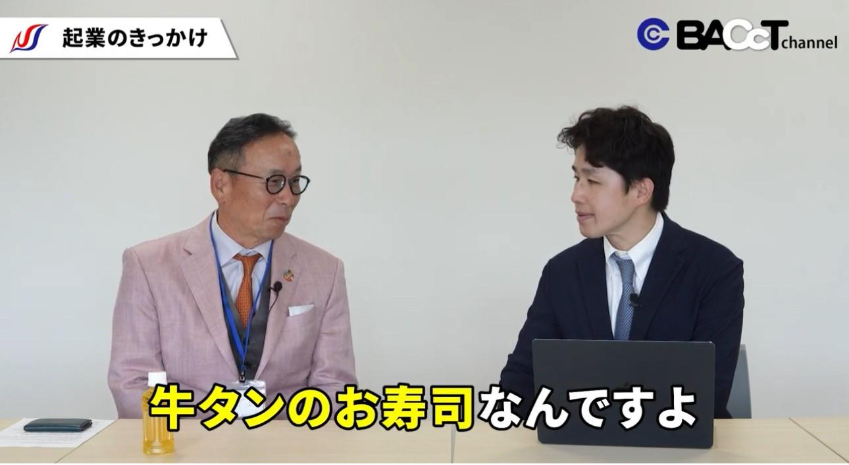
「お客様に喜ばれるものをつくりたい」——その想いが、今の事業の原点です。
もともと和食の板前だった社長が、ある施設に牛タンのお寿司を提供したところ、予想以上の反響がありました。「こんなに喜んでもらえるのか」と実感したその瞬間が、商品開発への第一歩。牛タンを軸にした新たなメニューを次々と生み出し、やがて駅や空港など、販路は全国へと広がっていきました。
しかし、社長の原点は料理人ではありません。若い頃はスポーツに打ち込んでいたものの、それだけでは生活が成り立たず、市場で働きながら生計を立てようと模索していました。そんな中、料理屋さんでの手伝いをきっかけに板前の道へ。お金を稼ぐために始めた仕事が、いつしか「楽しい」と感じられるようになり、料理の世界にのめり込んでいったのです。
②企業名の由来
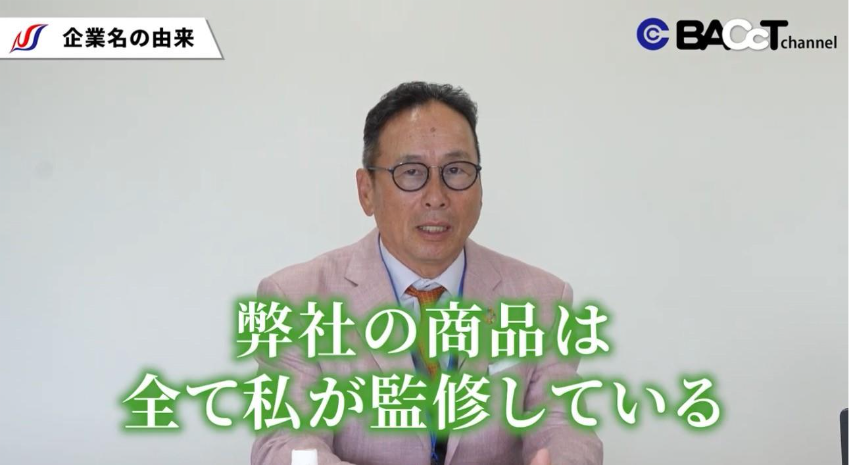
「陣中」という社名には、単なるネーミング以上の“覚悟”が込められています。
大阪でも店舗を展開していた社長が、宮城に拠点を移した際、牛タンの太巻き寿司を箱詰めして販売するようになりました。そのとき、「箱に何も書かれていないと寂しい」と感じ、商品に物語性を持たせるために一文を添えたのです。
「伊達藩陣中のみぎり、兵糧として腰にぶらさげ焼く時期となされたそうな…」
この一文が、商品に“お土産らしさ”と“歴史の香り”を添え、やがて社名「陣中」へとつながっていきました。商売とは戦いであり、自分自身との戦いでもある——そんな思いが込められています。
この姿勢は、衛生管理の現場にも通じます。日々の検査や改善活動は、目に見えにくい“戦い”の連続です。社長は、陣中で扱うすべての商品に自ら監修を行い、味付けや製法、工程に至るまで細部にこだわります。そして、それを工場スタッフとともに、量産可能な形へと落とし込んでいくのです。
現場での試行錯誤を経て、品質と安全を両立させる——そのプロセスこそが、衛生管理の本質であり、陣中のものづくりの根幹でもあります。
③苦しい時期は何度もあった
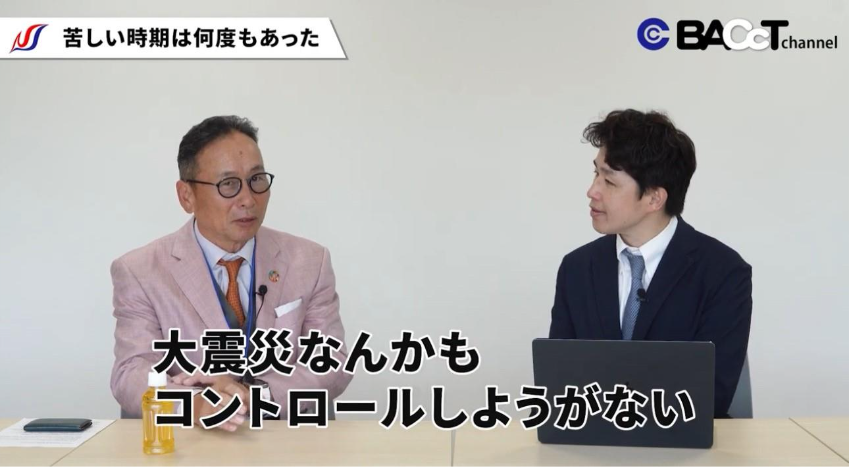
「勝ち戦より負け戦の方が万とある」——これは、陣中の社長が語る実感です。
事業の歩みの中で、何度も苦しい局面が訪れました。たとえば、牛タンを扱う企業にとって致命的だったのが、BSE(牛海綿状脳症)問題。仕入れ値を下回る価格でしか販売できず、飲食店展開していた高速道路や空港、駅などの販路にも大きな打撃を受けました。
さらに、工場を中国へ移転した直後には、国内で発生した“冷凍餃子事件”により、中国製品への信頼が揺らぎ、輸入商品が堂々と物販に並べられなくなる事態に。そして追い打ちをかけるように、東日本大震災が発生——いずれも企業努力ではコントロールできない外部要因です。
しかし、苦しいのはそれだけではありません。「美味しいものをお土産にする」こと自体が、極めて難しい挑戦なのです。
料理人がつくった料理は、1〜2時間後に食べても美味しい。しかし、それを1日、1週間、1カ月、半年と保存し、流通に乗せるとなると、話は別です。菌の繁殖、衛生管理、安全性——これらをクリアするには、料理人の技だけでは限界があります。
つまり、料理人の腕前と、工場の設備・環境に準じた製造方法を“ゼロから再設計”する必要があるのです。味を守りながら、衛生基準を満たし、安定した品質を保つ——この難題に挑み続ける姿勢こそ、衛生管理の現場に通じる“ものづくりの覚悟”ではないでしょうか。
④「復興・観光・環境」にかける想い

陣中の事業には、「復興・観光・環境」という3つの柱が据えられています。それは、東日本大震災を経験したからこそ生まれた、地域とともに歩む覚悟の表れです。
震災当時、前工場は幸いにも大きな被害を免れましたが、地域には600世帯もの避難者が小学校に集まっていました。そのとき、社員総出で牛タンを焼き、避難者の方々に振る舞った——その行動が、名取市長の目に留まり、閖上地区への工場建設という新たな展開へとつながっていきます。
閖上は名取市の中でも特に被害が大きかった地域。そこを「人が集まる場所にしたい」という市長の熱意に応え、陣中は6,000坪の土地に新工場を建設。津波が来ても逃げ場があるように、来訪者の安全を第一に考えた設計で、50年先まで耐えうる建物を目指しました。
この工場は単なる生産拠点ではありません。復興の象徴であり、観光の起点であり、環境と共生する地域資源でもあります。たとえば、夏休みには子ども食堂への参画や、敷地内のビニールハウスで育てたシャインマスカットを、地元の子どもたちが“ちぎって食べる”体験を提供。ファミリーやグループが楽しめるレクリエーションの場としても機能しています。
こうした取り組みは、震災後に生まれた「地域とともに生きる」という思想の具現化です。そして、その根底には、陣中が掲げる“4つの仕事”があります。
- 喜んでいただくコト
- 必要とされるコト
- 笑顔でいるコト
- 感謝するコト
これらを毎朝、従業員とともに三唱し、仕事の原点を確認する——そんな姿勢が、衛生管理の現場にも通じる“志”ではないでしょうか。安全・安心を守るだけでなく、地域に根差し、未来を見据えたものづくりを続けること。それが、陣中の衛生管理の本質でもあるのです。
⑤食品衛生に対する考え方
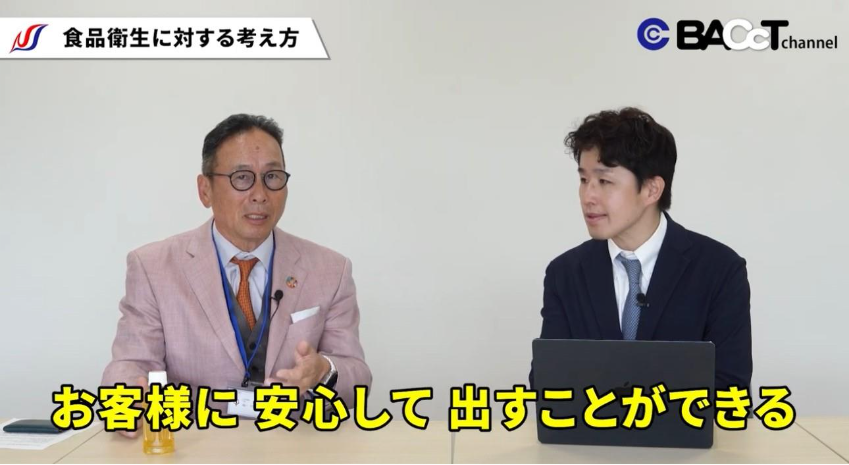
「お客様からの信頼なくして、商売は成り立たない」——これは、陣中が食品衛生に向き合う姿勢の根幹です。
食の安全は、企業活動の“前提条件”であり、美味しさを届ける以前にクリアすべき“責任”です。美味しいものをつくり、喜んでいただき、買っていただく——このサイクルを成立させるには、衛生管理が確実に機能していることが不可欠です。
社長はこう語ります。「食品衛生は、やらないと不安なものを出すわけにはいかない」。つまり、衛生管理は“やるべきこと”ではなく、“やらなければならないこと”なのです。
工場の衛生管理は、誰か一人の目だけでは成り立ちません。だからこそ、HACCPやFSSC22000といった国際的な衛生管理システムの導入が重要になります。これらの仕組みは、監視と記録を通じて、製造工程の安全性を“見える化”し、履歴として残すことで、お客様に安心を届ける基盤となります。
陣中では、「食べて結果が出るまでが、企業の責任」と考えています。売ったら終わりではなく、食べた後の体験までを見据えて品質を守る——この姿勢は、衛生管理に携わるすべての現場に通じる“プロ意識”ではないでしょうか。
美味しさの前に、安心安全を。これは、陣中が掲げる“ものづくりの哲学”であり、衛生管理の本質でもあります。
⑥FSSC22000を取得するメリット
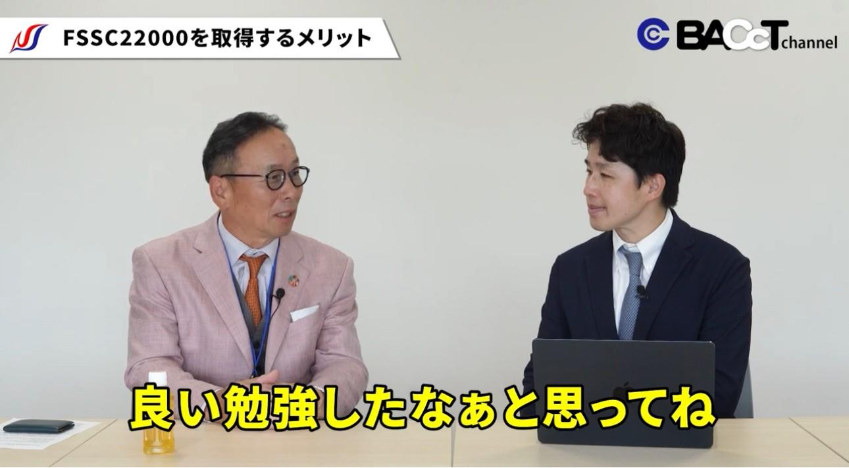
FSSC22000の取得は、単なる認証ではありません。それは、企業として「食の安全を守る覚悟」を示す信頼の証です。
陣中では、この国際規格を取得することで、取引業者さまに安心感を提供できるようになりました。新たな商談の場でも、「FSSC22000を取得している企業なら」と認めていただける機会が増え、事業の可能性が広がっています。
しかし、取得までの道のりは決して平坦ではありませんでした。社長は「容易く取れる資格ではない」と語ります。細かな基準に対して「そこまでやるのか」と思う場面も多く、最終審査では2名の審査員が工場に訪れ、徹底的なチェックが行われました。
この経験を通じて、陣中では衛生管理担当者への指導内容にも変化が生まれました。単なるルールの遵守ではなく、「なぜそれが必要なのか」「どうすれば現場で活かせるのか」といった“考える衛生管理”へと進化したのです。
FSSC22000の取得は、衛生管理の“仕組み化”を促すだけでなく、現場の意識改革にもつながります。記録を残すことで、工程の透明性が高まり、万が一の際にも迅速な対応が可能になります。これは、食品衛生に携わるすべての現場にとって、非常に大きなメリットです。
信頼を得るための制度を、現場力に変える——それが、陣中がFSSC22000に込めた想いです。
料理人としての技術だけでなく、原点にある“喜ばれるものをつくりたい”という想いが、陣中のものづくりを支えています。その姿勢は、衛生管理や商品開発にも一貫して息づいています。陣中の“安心の先にある美味しさ”は、あなたの衛生管理の視点にも届いたのではないでしょうか。
今回の動画はこちらです。
次の記事はこちらです。
【オムライス工場の品質管理】食品微生物検査の内製化への歩みと衛生への取り組みについて【品質管理インタビュー/ポムフード】